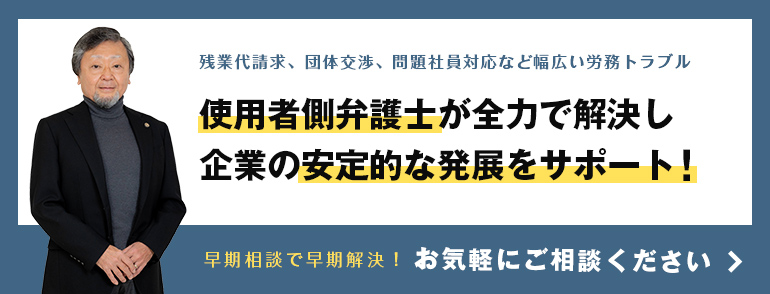労働審判意外と知られていない労働審判、その内容
「労働審判の申立書が届いたが、どのように対応すれば良いかがわからない」
「合意退職をした元従業員から不当解雇で訴えられてしまった」
「元従業員から過去に遡って残業代を請求されてしまった」
労働審判は、平成18年4月からスタートした、裁判所が行っている制度ですが、裁判所によって利用できないところもあります。裁判官と労使推薦の民間委員各1人の計3人によって構成される労働審判委員会が、事件を審理します。
労働審判は労働者側、使用者側のどちらからでも申立できますが、労働者側から申立があるのが普通でしょう。
審判の対象は個別労働関係に関する民事紛争です。解雇・雇止め・配転・出向・降格・賃金・時間外手当・退職金等使用者と労働者個人との間で生じる紛争全般が対象になります。ただ「個別労働関係」に関する事項に限られますので、使用者と労働組合との間の集団的紛争は含まれません。また、使用者たる会社が相手の場合に限られるため、代表者は上司個人に対する損害賠償は対象になりません。
調停は、裁判官1名(正式名称は「審判官」)と労使双方の委員が同席する中で行われます。経営団体から推薦された委員も、労組合全国組織から推薦された委員も、中立的立場にありますから、使用者側委員が使用者に同情的ということは全くなく、法意識が不足した使用者に対しては、使用者側委員の方が厳しい目を向けることもあります。
労働審判では、申立後1カ月以内に第1回期日が行われ、第3回期日までに調停がまとまらないと、審判(判決のようなもの)となります。通常、審判は、書面によらず、口頭で行われます。不服がある場合は、その日を含めて2週間以内に異議を申し立てることができ、その場合訴訟に切り替わります。
労働審判の特色は何と言ってもスピードであり、次のような特徴があります。
- 申立書の補充は原則許されない。
- 証拠も申立書と同時に全て出す必要がある。陳述書の提出も必須。
- 期日の変更を申し出ることができるのは、裁判所から申立が届いてから10日以内(できれば5日以内)。
- 答弁書の提出期限は期日の1週間から10日前。補充書面の提出は許されない。
- 第1回で審理が終了することがほとんど。
- 第1回期日に調停が成立することもある。
- 第1回には代表取締役の参加は必須。その他事情を知る役員、上司、同僚も出席することが有用。
- 第1回期日は午後全部を使って行われ、午後8時に至る場合もある。
審判は、委員3人、使用者側、労働者側の3者が同席する形で行われます。まず、裁判官から質問があり、その後、個々の委員から質問があります。審判は、委員の質問とそれに対する回答が中心で、労働者側、使用者側から積極的に発言するための場ではありません。代表者も委員から聞かれたら自ら答えなければならず、弁護士に代弁させることはできません。弁護士の役割は、あくまで補助的な立場にとどまります。
双方からの事情聴取が終わること、次いで、労使とも室外に待機させられ、委員3名で事件について協議します。そこでさらに事情聴取が必要なら、さらに事情聴取を行いますし、既に十分と考えれば、次いで調停に移ります。調停の場面では、使用者側、労働者側が交互に呼ばれ、委員との間で事件の落とし所を探ります。その場で、裁判官から心証(審判の見通し)も示されますので、その心証を前提に、労使双方が互いにどこまで妥協できるか、どこまで要求するかを、探り合う形になります。
話がまとまりそうだとなると、「鉄は熱いうちに打て」とばかりに、委員は懸命に双方を説得し、一気に調停成立に持って行こうとします。社長も出席していますから「会社に持ち帰って」といった弁会は通用せず、その場での決断が求められます。
団体交渉が行われないまま、あるいは、不十分なまま労働審判を迎えると、争点の所在が十分明確にならないまま、審理・調停を迎えるため、十分な審判の遂行ができません。また、労働審判において十分な主張・立証を行っておかないと、労働訴訟で不利な心証を持たれかねません。従って、最終的に労働訴訟で決着をつけざるを得ない事案でも、労働審判での対処が重要であり、それ以前に団体交渉の対処が重要なのです。
このように、労働審判は第1回期日が重要ですので、期日前には入念な準備が必要であり、調停案についても十分検討しておく必要があります。制度上、弁護士をつけることは求められていませんが、実際には弁護士をつけないで労働審判を戦うのは無謀です。期限の制約もあり、労働審判になったらすぐ依頼できる弁護士を日ごろから確保しておくことをお勧めします。
労働問題 メニュー
人事・労務 メニュー