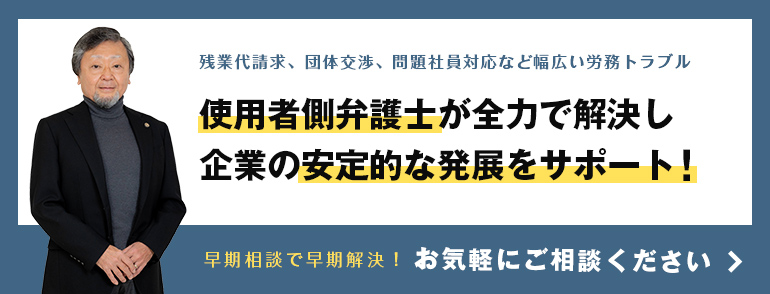- 弁護士による企業法律相談TOP
- 従業員の不祥事 - 従業員が逮捕されたら
従業員が逮捕されたら従業員が逮捕された際の初動対応の重要性
発覚
従業員が逮捕された場合、従業員が警察を通じて会社に連絡してくることはまずなく、多くは家族からの連絡で判明する場合がほとんどです。逮捕当初は、家族から「急病で病院に入院した」との連絡だったのが、逮捕後かなりたってから、隠しきれなくなって「実は逮捕されています」と連絡がくることもあります。
タイムスケジュール
警察は、被疑者(俗に言う容疑者)を逮捕後48時間以内に事件を検事に送致しなければならず、検事は事件の送致を受けてから24時間以内に釈放するか、裁判所に勾留を請求しなければなりません。裁判所は、通常10日間の勾留を命じますが、検察の請求を受けて、さらに10日間勾留することができます。検察官はこの間に、被疑者を起訴するか否か、起訴するとして身柄を拘束したまま起訴するか否かを決める必要があります。
被告人から情報が貰えるか
会社としては、容疑事実が何か、本人が否認しているのか、勾留はどの程度続きそうかを知りたいところでしょう。被疑者が重要な仕事を担当している場合、その引き継ぎも必要になります。会社としては当然家族から情報をとろうとすると思いますが、思うように情報が得られないことが少なくありません。
逮捕後送検されるまで(72時間以内)は警察の取調べ等が優先し、事実上、家族でさえなかなか会わせて貰えません。裁判所が勾留を許可する場合、接見禁止といって、面会禁止の処分をすることがあり、その場合、家族さえ面会を禁じられてしまいます。その場合は、弁護人しか被疑者に面会することはできません。
弁護士が弁護人として選任されているときは、その弁護士に連絡して、本人とのやりとりを仲介して貰うことを考えるべきでしょう。ただ弁護士は守秘義務を負っているので、会社が知りたいこと全てを教えて貰えるわけではありません。
従業員への休職命令の可否
当該従業員が勾留されている間は、自らの責任で会社への出勤が不能になっているのですから、会社が賃金(給与)を払う必要はありません。問題は、当該従業員が釈放され、出勤の再開を申し出てきた場合です。
会社は自宅待機を命ずることはできますが、その間賃金を支払う必要があります。但し、就業規則に、「起訴休職」の規定があれば、この規定に基づき休職を命じ、賃金を全部ないし一部を不支給とすることができます。
従業員が次の各号の一に該当するときは、休職を命ずる。 ● 刑罰法規に違反して起訴され、刑の確定しないとき
前項に定める休職期間中は、給与の全部または一部を支給しない(所定労働日数1日につき本給の月間基礎日数分の1を控除する)。
刑事訴訟手続における無罪推定原則から、起訴休職制度を無効とする見解もありますが、次のように条件付で認めるのが、裁判所の通常の見解かと思われます。
いわゆる起訴休職制度は、…刑事裁判が確定するまで従業員としての身分を保有させながら一時的に業務から排除して、企業の対外的信用の確保と職場秩序の維持をはかり、労務提供の不安定に対処して業務の円滑な遂行を確保するにある。
右のような起訴休職制度の趣旨・目的からすると、当該従業員を起訴休職に付することができるのは、当該従業員が起訴されたこと又は起訴後も引き続き就労することによって、企業の対外的信用が失墜し、又は職場秩序の維持に障害が生ずるおそれがある場合、あるいは、当該従業員の労務の継続的な給付や企業活動の円滑な遂行に障害が生ずるおそれがある場合に限られると解すべきである。(東京地裁平成15.5.23判決 山九事件)
それでは、休職事項を定めるについて、起訴休職規定がなく、「特別の事由があって休職させることを適当と認めたとき」といったような包括的な規定しか置かれていなかった場合はどうなるでしょうか。
上記山九事件がまさにそういった場合だったのですが、裁判所は「「特別の事由があって休職させることを適当と認めたとき」とは、当該労働者の就労を受け入れることによって業務に具体的な支障が生じ、かつ、そのことが労働者の責めに帰すべき事由に基づく場合であることを要するものと解するのが相当である。
すなわち、労働者の労務提供に瑕疵があり、使用者においてその受領を拒絶することに正当な理由があるといえる場合でなければならないというべきである。」と述べ、厳格な制約のもとではありますが、会社は起訴された従業員に対して同規定を根拠に休職を命じうるとしました。そして従業員の「起訴休職についての明文がない以上、抽象的な定めをもって、起訴を理由とする休職を命じることは罪刑法定主義に反し許されない。」との主張に対しては「労働者の責に帰すべき事由による瑕疵ある労務提供について、あらゆる事態を想定して具体的に記載することはむしろ不可能であって、前記記載の程度で足りる」として、その主張を退けています。
しかし、起訴休職規定があったとしても、必ずしも休職命令が認められる訳ではありません。実際上記の山九事件では、休職命令は無効とされ、休職期間中の賃金支払い義務が認められています。ですから、従業員から、極力休職願いをとりつけるようにすべきです。こうして「従業員が自由な意思で休職を願い出、会社がこれを認めた」という形を作り、自己都合による休職であり、賃金支払い義務は無い、とすべきでしょう。
従業員の解雇の可否
従業員が、勤務時間外で事件を起こし、逮捕された場合、会社は解雇できるでしょうか。就業規則では、普通「不名誉な行為をして会社の体面を著しく汚したとき」とか「犯罪行為を犯したとき」を普通解雇ないし懲戒事由としています。
しかし、労働契約法15条は、「当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。」とあり、同16条は「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定しています。 会社は、企業の存立と事業の円滑な運営の維持のため、企業秩序を定立し維持する「企業秩序定立権」を当然に有しており、従業員は雇用されることによって、労務を提供する義務を負うとともに、この企業秩序を遵守する義務を負っています(最高裁昭和52.12.12判決・富士重工業事件、最高裁昭和58.9.8判決・関西電力事件)。会社は、企業秩序を維持するため、これを侵害した従業員を懲戒処分することができます。業務外の犯罪行為は企業秩序定立権の外にあり、これを理由に懲戒することは権利濫用にあたる可能性があります。
ただ、営利を目的とする会社であっても、その名誉、信用その他相当の社会的評価を維持することは、会社の存立ないし事業の運営にとつて不可欠ですから、会社は「社会一般から不名誉な行為として非難されるような従業員の行為により会社の名誉、信用その他の社会的評価を著しく毀損したと客観的に認められる場合に、制裁として、当該従業員を企業から排除しうること」は可能と考えるべきです(最高裁昭和49.3.15判決・日本鋼管事件)
ただ、従業員の当該犯罪が、経営者や従業員らの有する名誉感情を害しただけでは、起業秩序定立権を侵害するものとは言えず、社会一般の客観的評価を害したことで初めて懲戒処分を行う合理的理由があるといえます。ですから、「従業員の不名誉な行為が会社の体面を著しく汚した」こと、「犯罪行為を犯した」ことが、懲戒の対象となるためには、必ずしも具体的な業務阻害の結果や取引上の不利益の発生を必要とするものではないとしても、「当該行為の性質、情状のほか、会社の事業の種類・態様・規模、会社の経済界に占める地位、経営方針及びその従業員の会社における地位・職種等諸般の事情から綜合的に判断して、右行為により会社の社会的評価に及ぼす悪影響が相当重大であると客観的に評価される場合」でなければなりません(前記日本鋼管事件最高裁判決)。
最高裁昭和45.7.28判決(横浜ゴム事件判決)は、従業員が深夜、他人の住居の風呂の扉をはずして侵入したことで、住居侵入罪に問われ罰金2500円を科せられ、これを理由に懲戒解雇されたという事案に関するものですが、最高裁は「右賞罰規則の規定の趣旨とするところに照らして考えるに、問題となる被上告人の右行為は、会社の組織、業務等に関係のないいわば私生活の範囲内で行なわれたものであること、被上告人の受けた刑罰が罰金2、500円の程度に止まつたこと、上告会社における被上告人の職務上の地位も蒸熱作業担当の工員ということで指導的なものでないことなど原判示の諸事情を勘案すれば、被上告人の右行為が、上告会社の体面を著しく汚したとまで評価するのは、当たらないというのほかはない。」と判示して、会社側の上告を棄却しました。
ですから、判決による刑が重く、当該従業員が社内で責任ある立場にあり、他の従業員との不和を生じる恐れがあり、犯罪の内容が会社の業務に支障を与えるようなものであるとの事情がある場合は、懲戒の対象となりやすいと言えるでしょう。
私鉄電車の従業員が、他の私鉄線で痴漢行為を行い、罰金20万円との判決を受け、会社が懲戒解雇とした事案で、裁判所は、当該従業員が以前にも痴漢行為で2回罰金刑を受け、その際も昇給停止、降格処分を受けていたことのほかに、会社が痴漢撲滅のキャンペーンを行っている中で痴漢事件を起こしたことが世間に知られればイメージダウンになりかねないことも理由にして、懲戒解雇を有効と認めました(東京高裁平成15.12.11判決・小田急電鉄事件)。
刑自体は軽くても、会社の事業内容から、当該犯罪が会社に大きなダメージを与えることを考慮したものと言えるでしょう。
退職金の支給
刑事訴訟では、無罪推定が働きますから、有罪判決が出るまでは、懲戒解雇はなしえません。そこで、従業員が先手を打って、有罪判決が出る前に退職届を出してしまうということが考えられます。退職してしまえば、懲戒解雇もなしえず、そうすれば退職金を支給せざるを得ないことになります。
ですから、会社としては次のような規定を就業規則に定めておく必要があります。
退職後退職金支給前に、在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが発覚したときは、退職金を支給しない。
退職金支給後に、在職中に懲戒解雇に相当する行為を行ったことが発覚したときは、既に支給した退職金の返還を求めることができる。
退職前に、犯罪行為を行ったことが発覚したが、退職後退職金支給前ないし退職金支給後に有罪判決が確定した場合も、前2項の例による。
上記の規定がない場合は、退職届発効前に、更に先手を打って懲戒解雇処分を行うことです。有罪判決が出る前であっても、当該従業員が起訴事実を認め、単に情状を争っているだけであれば、懲戒処分が有効とされる場合もあるだろうと考えるからです。
従業員の不祥事 メニュー